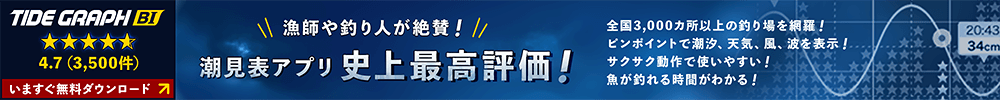MONTHLYランキング
迷いを断てばフカセチヌは爆釣必至! G杯覇者・沖永吉広が実践するG5オモリ使用術
チヌの魚影の濃さで知られる芸予諸島。
東は福山市から西は江田島市まで、また、南に目を向けると愛媛県下にまでまたがる広大なエリアには、大小さまざまな島が点在し、その影響もあって潮の流れは複雑で、ゆったりとした潮が流れるかと思えば、次の瞬間に激流へと変貌するような刻々と状況が変わる釣り場となっている。
今回はG杯争奪全日本がま磯(チヌ)釣り選手権を制した経験を持ち、チヌのトーナメントでは上位入賞の常連でもある波多瑞紀さん、沖永吉広さんの両者が、乗っ込みのチヌを狙って芸予諸島の豊島へ釣行。
その中で、メインとなったのが常にトーナメントを意識した釣りを展開する2人の釣りスタイルだ。
プライベートでの釣りにおいても、1投の無駄、仕掛け交換などの時間のロスを徹底的になくすスタイルは一種独特の考え方ともいえる。
今回は、そんな中でG杯チヌを2度制した実力派トーナメンター・沖永さんの独特な釣法を紹介してみたい。
目次
芸予諸島で名手2人がチヌを釣りまくり
常に競技を意識してのシステムには、こだわりがいっぱい
「トーナメントでは、振り返ってみると、あの1尾を取り込めていれば…、あの無駄な1投がなければ…という理由で負けちゃうことがよくあるんです。そんな無駄な1投や仕掛け交換の時間などのタイムロスをできるだけなくしたい…それが僕の普段の釣りなんですよ」と話すのは沖永さん。
G杯チヌを2度も制した実力派だからこその言葉かもしれないが、それを普段のプライベートの釣りでも常に心がける。
それは今回競演した波多さんも同じで、2人で釣行すると常に競技を意識した釣りになるとか…。
渡船の中でも情報交換は欠かせない
ウキはトップ交換式の自立式棒ウキ。オモリはG5以外使わない理由
そんな沖永さんが、今回の舞台である豊島の石切で使用したタックルから紹介していこう。
まず、竿は「がま磯 アテンダーⅢ」1.25号5.3m。
レバーブレーキ付きのスピニングリールに、道糸はセミサスペンドタイプの1.5号、ハリスは1.75~2.5号を2ヒロほどに、鈎は「G-HARD V2 チヌエース」1号と「G-HARD V2 貫チヌ」1号を使い分ける。
ウキは00表記の自立式棒ウキ(遠矢ウキ)に、オモリはジンタン5号(G5)で調整する。
「がま磯 アテンダーⅢ」1.25号5.3m
鈎は「G-HARD V2 チヌエース」「G-HARD V2 貫チヌ」で、ともに1号を主流にしている
「チヌ釣りとしては、ハリスを2.5号まで持参しているのは珍しいと思います。ただ、この石切は島から切り出した大きな石が海中にも入っていて、大型チヌになるとほとんど石でできた障害物周りへと突っ走ります。どうしても根ズレなどが出るので釣り座によっては太いハリスが必要になるんですよ」と話す。
そして、特徴的なのが自立式の棒ウキだ。
実はこのウキ、ボディとトップが分かれていて、1つのボディに対して、トップは6~7本を交換できる仕組み。
トップを交換式にして状況対応させやすくしている棒ウキのシステム
「海の状況やチヌのアタリの出方によって、トップを交換していくんです。たとえば、逆光で見えにくければ太いトップに替えるとか、少しボディを沈み気味で使いたければ長いトップにするなどなんですが、ウキ自体を交換するとなるとタイムロスにつながります。そこでトップだけをすぐに交換できるようにバッカンの横に立てておくんです」と言う徹底ぶり。
バッカンの縁に棒ウキセットが設置されている
そして、ボディの浮力表記である「00」だが、棒ウキの場合は円錐ウキと違い、表記よりもかなり余浮力がある。
棒状のウキである分、ウキを引き込む際に抵抗を感じにくくなっているので、余浮力があってもチヌが違和感なく食ってくれるからだ。
そんな余浮力を持たせたウキに対して、使うオモリはジンタン5号、つまりG5オンリー。
その理由をうかがうと「いろいろな重さのオモリを持っていると、どのくらいの重さを背負わせようか…と迷うじゃないですか。だから僕は、その選択の迷いをなくすためにG5しか持たないようにしてるんです(笑)」。
つまり、仕掛けを重くしようと思えば、G5を足して打っていく。
オモリ交換の迷いを断つことも、チヌ爆釣劇への準備でもある。
G5を追加、減少を繰り返してチヌの食う状況を作り出していく
棒ウキで海中の状況把握を素早く行う。トップのみ交換の時短成功チヌ作戦
さて、実はこの日、先に釣り始めた波多さんは、自重のある小型棒ウキでの遠投スタイルを得意とする。
特にこの場所では乗っ込み時に沖のマキエでチヌを集めて浮かせることで、警戒心の低いチヌを簡単にヒットさせることができるからだ。
3投目に早くも竿を大きく曲げた波多さん。
いきなり46cmのチヌを仕留めた。
開始後3投目で波多さんが良型チヌを仕留めた
「3投目ですよ~」と少し離れた場所から声をかけた波多さんに対して、沖永さんは波多さんよりも少し手前にマキエを集中させた後、仕掛けを投入した。
その2投目に棒ウキの頭を押さえたかと思ったが、モゾモゾッと動いた後にゆっくりとウキが海中へ。
しかし、これは素鈎。
ただ「チヌいますよ。次の3投目で釣ります(笑)」と言うと、G5のオモリを1個、ハリスの真ん中に足し、ウキ下を少し浅くした。
そして、宣言の3投目。
ウキがスパッと水中へ入り、チヌがヒットした。
このチヌは49cmと、年なしには少し足りなかったが大型のきれいなチヌだった。
沖永さんの3投目に早くも「アテンダーⅢ」がきれいな曲がりを見せる
50cmに1cm足りなかったが、49cmのきれいなチヌをキャッチ
ウキへのアタリは確かに本命のチヌと確信した沖永さんは「チヌのタナが浅くて、おそらくサシエが沈んでいる最中に食ってきていると思ったんです。そこで、ウキ下を浅くして、仕掛けのなじみを速くすることでアタリを明確に出させようと思ったのが正解でした」と話してくれた。
棒ウキだからこその判断なのだが、実はこの場所は朝日が真正面から昇り、ウキが見辛い状況。
そこで、1投目を回収した直後に棒ウキのトップを太いタイプに替えていたので、2投目の反応が手に取るように分かったのだ。
見辛い状況のままなら…、見にくいのでウキを交換する時間を要していたら…と思うと、沖永さんの考え方が正解であったのかも。
釣りの基本は「仕掛けを立てる」こと! 再現を求めて釣れたタナの把握を第1に考える
この日、朝からチヌを立て続けに釣り続け、2人ともが45~46cmをアベレージに2ケタ釣果をたたき出したのだが、ここにも沖永さんのシンプルな迷いを断つこだわりがあった。
「実は僕は仕掛けが立っていないと、釣れそうな気にならないんです。と言うか、連発で食いを再現させたいので仕掛けを立てた状態を作るんですよ」と沖永さんは話す。
通常、フカセ釣りの基本はサシエ先行で、潮に乗せてサシエがウキを引っ張るような状態が理想とされている。
魚が潮上から流れてくるエサを待ち受けていることや、サシエが先行して仕掛けが斜めになることにより、ハリスを見えにくくするためともいわれている。
逆にウキが仕掛けを引っ張るような状況下では、魚は食わないとも…。
ところが、沖永さんの考え方は少し違う。
それがオモリ使いである。
仕掛けが立っていないと連発する気がしない…というのは、チヌが食うレンジの話。
仕掛けが軽いと、確かに自然にサシエが潮に乗って流れ理想的な形を作りやすい。
しかし、潮に吹かれる分、サシエが巻き上がったり、浮いたり、まっすぐに沈んだりと微妙なタナに関しては不安定だ。
そこで、沖永さんは仕掛けを安定させ、ウキ下をきっちりと設定するためにオモリを使う。
この日も潮がゆっくりと流れている状況でも、思った方向に仕掛けがいっていない時にはオモリをどんどん足していた。
仕掛けを立ててチヌの食うタナを完全把握すればチヌは入れ食いだ
棒ウキを使っていると、ウキの傾きでウキより下の仕掛けがどちらに流れているかを把握しやすい。
そこで仕掛けが斜めになっていると、ウキ下の微妙な設定が不安定になるため、ウキより下の仕掛けが垂直になるようにオモリを足す。
それも、フカセ部分が長いと潮によって流されるので、極力フカセ部分を短くするように、段シズ仕様(ガン玉を複数打つ仕様)の仕掛けにする。
つまり、チヌが食ってくるタナを微妙な単位で把握することで再現性を持たせて、連発に持ち込む。
段シズは通常サラシなどで水中の仕掛けが安定しない時などに使用することが多いが、それよりもさらに仕掛けを垂直に立てるために使うのが沖永流だ。
そして、使うオモリはジンタン5号、G5のみ。
「オモリも号数がいっぱいありますよね。釣りをしている最中にどのオモリを使うか…を迷うとタイムロスにつながります。その上で、あっこの重さじゃなかった…ということにもなりかねます。そんな迷いを断つことでタイムロスをなくして、自分の仕掛けで通すことにしているんです」と沖永さんは話す。
なので、沖永さんがもっとも多用するG5のみをベストに入れ、それだけですべてを調整する。
その結果、潮がゆったりと流れているような場面でも、3段打ち、5段打ちとなることもある。
そして、ここでも棒ウキのメリットが生かされる。
前述のように棒ウキは余浮力が強く、00号の表記であっても、ガン玉Bや2Bを打っても沈むことはないので、少々G5を多くしても問題なくそのまま釣り続けることができる…という寸法だ。
操作性の高い竿だけじゃない! 突如として掛かる大チヌに対処できるパワーも欲しい
今回、沖永さん、波多さんとも使用していた竿が、がまかつ渾身の磯竿である「がま磯 アテンダーⅢ」の1.25号5.3m。
チヌ釣り用としては、このシリーズの中では0号や06号、1号でも十分なのだが、時として障害物へ突っ走る大型チヌを止める必要があるため、ワンランク以上パワーのある竿を選んだ。
波多さんが遠投でチヌを掛けるときれいな曲がり込みでチヌを楽々寄せていた
この「アテンダーⅢ」シリーズの特徴としては、仕掛けの投入やラインメンディングなどの操作感は先調子そのもの、魚が掛かれば胴から曲がり込んで粘りで魚を勝手に浮かせてくれる胴調子でありながらも操作性を秘めたことから、幅広い用途がある点が挙げられる。
胴から曲がり込んで魚とやり取りできるので、ワンランク細いハリスが使えるというメリットがあるのだが、今回2人が1.25号という号数を選んだのはそれだけではない。
というか、逆の発想だった。
実はワンランク太い竿を使っても、魚のサイズに合わせてしっかりと曲がり込んでくれるので、竿のオーバーパワーがないのがワンランク以上太い竿を安心して使える理由だ。
ちなみに、この日チヌがヒットしている合間に、沖永さんの仕掛けにコブダイ(カンダイ)らしき魚がヒットした。
最初に突っ走った引きから「チヌじゃない、コブダイですよ! でも取り込みますよ~」と言った沖永さんは「アテンダーⅢ」を胴から曲げ込むパワー勝負に出た。
この曲がり込みでカンダイの引きを真っ向から受け止める沖永さん
驚くほど曲がり込んだが、バット部分のパワーでコブダイの引きを受け止めて、見事に60cm近いコブダイを取り込んだのには驚かされた。
60cm級のカンダイを見事に取り込んだ
「40cm級のチヌでもしっかりと曲がり込んで楽しめる竿なんですが、こんなコブダイがヒットした時のパワー勝負でも無理ができる。汎用性の高さが非常に気に入っています」と沖永さん。
これはトーナメントの際に、突然大型チヌがヒットした時などにも十分対応できるし、プライベートの釣行においても、突然の大物を取り込むことができる強い味方となる。
●交通:山陽自動車道「福山西」ICで降り、松永道路をしまなみ海道方面へ。「高須」ICで降りてすぐを左折。道なりに直進して東尾道橋を渡ってすぐを右折し、黒崎水路、大田川沿いを南下し、山波東橋手前を左折して道なりに進む。
●問い合わせ:アクアテック(TEL:090・9733・1457)
(文・写真/松村計吾)
「棒ウキの達人が競演 瀬戸内海乗っこみチヌ」
※当日の様子は、YouTubeフィッシングDAYS「棒ウキの達人が競演 瀬戸内海乗っこみチヌ」https://youtu.be/Ig5Os8uQhqU で視聴できる。
ライター紹介

松村計吾
大学で水産無脊椎動物の研究を経て、釣り出版社に入社後、30年以上釣り雑誌や釣り情報紙の編集を手掛ける。取材などで釣りの現場に出ることはもちろん、休日などのプライベートでも常に釣りシーンにハマっている。得意な釣りは船のテンヤタチウオ、カワハギ、エギング、イカメタルなどだが、日本全国を飛び回りあらゆる釣りを経験。ちなみの甲子園の年間シートも所持。甲子園でのビール消費量も球界一とか・・・。
「磯釣り」カテゴリの人気記事
- 磯竿はどれを選べばいいの?初心者にも分かりやすいおすすめ人気アイテム11選
- 磯竿の3号ってどんな使い道があるの?人気メーカーのおすすめロッドをピックアップ
- ダイワの磯竿ってどれを選べばいいの?人気シリーズからおすすめロッドをピックアップ
- シマノ ブルズアイは磯カゴ専用リール!コンパクトで非常に使いやすい特徴やインプレ評価をご紹介!
- がま磯アルデナ特集!コスパ優秀ながまかつの磯竿を徹底チェック
- シマノの磯竿で釣りを楽しみたい!エントリーモデルからハンエンドスペックモデルまで徹底チェック
- 銀狼は2024年ダイワから新登場のチヌ釣り専用コスパ優秀ロッド!
- アテンダーIII 0号5.3m VS. 激流チヌ! 潮止まりはポイント作りに専念すればチヌが爆釣する!?
「釣具(タックル)」カテゴリの人気記事
- 釣りでエアーポンプを使いたい!選ぶポイントとおすすめ12選をご紹介
- 釣り入門セットの選び方とおすすめ10選!初心者必見のロッド&リールもご紹介!
- タモ網のおすすめ14選!玉の柄など釣りで一緒に使いたいアイテムもご紹介!
- バッカンってどんなふうに使うの?ダイワ・シマノなど便利なおすすめバッカン特集
- 釣りの三脚=ロッドスタンド特集!人気メーカーのおすすめアイテムを徹底チェック
- マルチランディングポールは2024年ダイワから新発売の軽さと強さを備えたタモの柄!
- カストキングのタックルってどうなの?ネット通販サイトで購入可能なコスパ優秀釣具をチェック
- ギャフってどんなふうに使えばいいの?エギングに欠かせないランディングアイテム