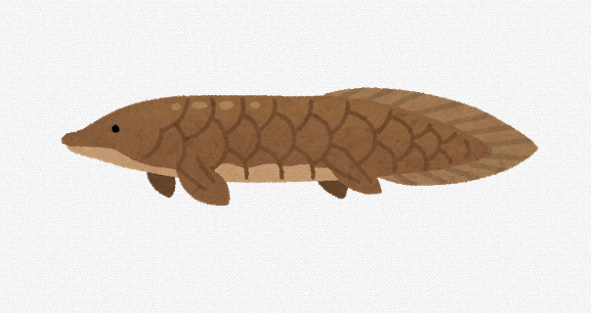ヒイラギって魚知ってる?釣り方からさばき方、おすすめの料理法まで一挙ご紹介!
みなさんは“ヒイラギ”をご存知ですか? 恐らく最も馴染み深いのはクリスマスに飾る植物だと思いますが、実は魚の中にもその名を持つものがいます。 防波堤釣りなどで群れになって泳ぐ…
FISHING JAPAN 編集部

まるで空を飛ぶ怪獣ギャオスのような頭が個性的な、海に泳ぐ魚・コバンザメです。
サメという名前から、がっつり噛み付いてくる狂暴な印象を持つかもしれませんが、どうやら別の種類の魚だそうでう。
あつ森でもかわいいと人気で、海を眺めて背びれの飛び出た魚影を見つけたら、竿を出してみましょう。
サメでないとしたら、一体どのような魚なのか、どんなふうに生きているのか、興味が湧いてきますよね。
今回は、そんなコバンザメの実際の生態や特徴について、詳しくご紹介していきます。
目次
コバンザメとは、スズキ目コバンザメ科の魚のことです。
サメではなく、魚だといわれても、結構フォルムがサメ寄りですよね。
熱帯・亜熱帯エリアに広く分布しているので、世界中でよく知られている存在のようです。
泳いでいる深さは、だいたい20メートルから50メートルくらいまで。
大型の海洋生物、例えばウミガメや巨大魚などにくっ付いて生活しているのが特徴で、なんと船にまでくっつくことがあるそうです。
コバンザメのイラストを探してみるとこんな感じで、かなりかわいい雰囲気に仕上がっています!
コバンザメが成長すると、最大で1メートルを超えるほどの体長になりますが、よく見かけるのは70センチくらいのものでしょうか。
頭部の背中側に小判のような形をした吸盤があって、これを使って大型のサメやウミガメ・カジキ・クジラなどに吸い付きます。
そしてそれら海洋生物が食べたエサのおこぼれを、横からかすめ取って生きているわけです。
また海洋生物に付いている寄生虫や排泄物を捕食しているケースもありますよ。
こういうコバンザメの生活スタイルを、片利共生と呼びます。
「なぜ片利なの?」
読んで字のごとく、片方にだけメリットのある共生スタイルだからです。
コバンザメはおこぼれを食べて生きていけますが、ウミガメはコバンザメから何ももらっていませんよね。
「えっ、でも体に付いた寄生虫を取ってもらっているじゃん!」
なるほど、もしかするとコバンザメのことをとてもありがたい存在だと思っていることもあるかもしれませんね。
コバンザメは、サンゴ礁エリアに棲み付いているケースも見られます。
その場合は共生スタイルではなく、単独で泳いでいることもあるようです。
サンゴ礁の周囲にいるエビや小魚を捕食する習性を持っていて、水質をキレイに保ってくれる役割を果たしています。
「海の掃除屋さん」というようにイメージすると、評価は一気に上がりますね!
実際にサンゴ礁の多い国々では、コバンザメを重宝に感じていることもあるのだとか。
これで食べて美味しければ、いうことなしですね。
コバンザメを食べている動画を見つけました。
丁寧に包丁を入れながらさばいていて、とても分かりやすく作業しているのが印象的です。
食べる習慣がひんぱんに発生すれば、もっと身近な存在になることは間違いなさそうですね。
しかし、魚屋さんに足を運んでも、コバンザメが並んでいるのは見たことがありません。
この動画のように、さばき方や料理の方法が分かれば、食べることにチャレンジする人が増えてくるでしょう。
そうなると魚屋さんも、コバンザメを仕入れざるを得ない展開に。
ぜひどんな味なのか、自分でさばいて食べてみたいものですね。
コバンザメの産卵期は、夏から始まって秋の間に行われているみたいです。
外洋性の生物なので、普段はオープンシーズで過ごしているのでなかなか目にすることができません。
しかし、産卵期が近づくと、沿岸に近いエリアまで出てくる習性があります。
もしコバンザメを釣りたいのであれば、この出現タイミングを逃さないことが大切です。
しかし、どのような道具やエサを使用すれば良いのでしょうか?
その話は後ほど、ゆっくりと考えてみましょう。
コバンザメ最大の特徴といえば、頭部の背中側に付いている吸盤の存在です。
よくこんな機能を持ったものが、身体の表面に現われたな!と思ってしまいますよね。
海洋生物の体に強力に吸い着いて、カンタンには離れてしまわない構造になっていますよ。
吸盤には複数のスリットが入っていて、吸い着くと後ろ向きに倒れるようになっています。
それが吸着を生む構造ですから、外したければ前方にスライドさせれば、ポロリと取れます。
スキューバダイビングなどで足や太ももに吸い付かれても、前ずらしで取ってみてくださいね。
それでは、コバンザメを釣るためのおすすめタックルをご紹介しましょう。
沖縄や九州地方の防波堤から、餌を付けて投げ釣りスタイルで釣っているケースがあります。
餌は、小魚やエビ・ゴカイなどの虫系で対応できますよ。
タチウオ釣りの餌でよく用いる、キビナゴなどを転用してみてはいかがでしょう。

シマノ(SHIMANO) パック&モバイルロッド フリーゲーム XT スピニング 5本継ぎ S76ULS アジ メバル 専用ケース付
シマノ製の振出式ルアーロッド、フリーゲームの紹介です。
その長さは8.6フィート、自重は140グラムで、ライトタックル寄りの特性を持ち、簡単に釣りの楽しさを体験することが可能です。
キャストできる最大重量は35グラムで、10号程度のオモリや天秤仕掛けを用いて投げ釣りを行うと、コバンザメにも届く可能性があります。
折りたたんだ際のサイズは74.1センチとコンパクトなので、車に常時積んでおくことで、いつでも釣りが可能な状態を保つことが推奨されます。
大型の魚を狙う場合やより遠くへ投げることを望む場合は、より長いフリーゲームを選択すると良いでしょう。

シマノ(SHIMANO) 19 ソルティーアドバンス ショアジギング S100MH
ショアジギング用の2ピースロッドです。
MHパワーですから、大型のコバンザメが掛かってもじゅうぶんにやり取りできるでしょう。
キャスト可能なウエイトは、80グラムまで。
これなら遠投の利くジェット天秤も活用できますね。
自重297グラムと300グラムを下回る扱いやすさですから、しっかりとフッキングもこなすことが可能です。

シマノ(SHIMANO) スピニングリール 19 ストラディック 4000XG サーフ ヒラスズキ ライトショアジギング・キャスティング
シマノのストラディック4000番なら、4号ラインを150メートルも巻けるので、遠投することもコバンザメの引きにも耐えることができるでしょう。
もっと太いラインを使いたいなら、リールの番手を上げてみてください。
自重280グラムでギア比5.3対1、扱いやすい設定なのでキャストを繰り返しながら、広範囲にポイントを探ってみるのが効果的でしょう。
早く巻き上げたい場合は、ギア比の高い機種を選んでアプローチしたいですね。

重さ10号の天秤です。
これにハリスとフック、そして餌を付けてキャストしてみましょう。
ハヤブサの立つ天秤なら、ボトムに落としても根掛かりしにくく、リトリーブを開始すると一気に浮き上がってくれますよ。
ハリスは太目でフックも大き目がいいでしょう。
ノマセ仕掛けのイメージで、カンタンに折れたり曲がったりしないフックを選びたいものです。

金龍の製品であるこのフックは、のませ専用です。
漁師が利用する太軸タイプのアジ鈎型のフックで、大型の青物をターゲットに設計されています。
小魚のような生餌を堅持しつつも、高い貫通力と太軸の強靭さを併せ持っています。
少ないバラシの評価が高いので、コバンザメ釣りも十分に対応可能でしょう。

釣り場近くで、生餌が手に入らない場合を想定して、このパワーイソメも持参しておきましょう。
虫系の餌も捕食するコバンザメですから、このワームも食べてくれる可能性があります。
アジングタックルなどで、餌となる小魚を先に釣る!という手段もあるのですが、うまく釣れなかったときは、ワームなどのルアーで代用できる備えをしておくのも大切です。
フックにふさ掛けにして、ボリューム感を出すようにしておくと、アピール度が増して食い付いてくれるかもしれませんね。
コバンザメの生態や特徴・実食動画や、おすすめの釣りタックルをご紹介しましたが、いかがでしたか?
なかなかコバンザメを釣る機会には恵まれませんが、もし沖縄や九州地方へ出向くならチャレンジしてみても面白いかもしれませんね。
携帯しやすい投げ釣りタックルを持参して、地元で有効な餌を調達したら、いざフルキャスト!
大物が掛かっても取り込みできるように、ランディングネットは必ず持参するようにしましょう。
ヒイラギって魚知ってる?釣り方からさばき方、おすすめの料理法まで一挙ご紹介!
みなさんは“ヒイラギ”をご存知ですか? 恐らく最も馴染み深いのはクリスマスに飾る植物だと思いますが、実は魚の中にもその名を持つものがいます。 防波堤釣りなどで群れになって泳ぐ…
FISHING JAPAN 編集部エソってどんな魚?実は高級食品の原材料!?エソの食べ方をご紹介!
上の写真に映っている魚の名前をご存知ですか。 この魚の名前はエソです。 エソはタチウオやアジ等を狙っている時に外道として釣れるので、実際に見たことがある方もいるかもしれません…
FISHING JAPAN 編集部古代魚を水槽で飼育してみたい!熱帯魚で人気の高い古代魚を集めてみた
何やら化石が泳いでいるかのような姿をしているのは、古代魚と呼ばれる魚です。 熱帯魚ショップなどで実際に販売されていて、特に大型に成長するものや珍しい形・習性を持つものは、人気が…
FISHING JAPAN 編集部MONTHLYランキング