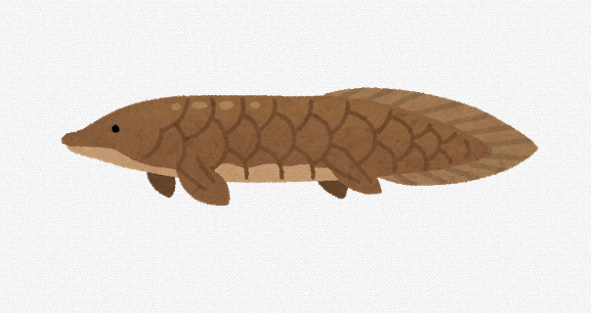ウナギ釣りを完全解説!天然うなぎの釣れる時期、エリア、仕掛けなど全てに答えます
近所の河川や都会のオフィス街の河川でもウナギが釣れることを知っていますか? さらにウナギ釣りはシンプルな仕掛けで挑戦でき、難しいテクニックも不要なので初心者でも簡単です。 こ…
FISHING JAPAN 編集部

海に棲んでいるウナギのような生き物といえば、アナゴを思い浮かべますが、写真はちょっと違いますよね。
これはドロドロの体液を大量に分泌することで知られている、ヌタウナギです。
韓国では一般的な料理にも使われる食材ですが、日本国内ではあまりみかけません。
いったい生息域はどの辺りなのか、その釣り方・調理方法などもチェックしてみましょう。
「ウナギに似ているんだから蒲焼きじゃないの?」
実は似ているのは外観だけで、ウナギの一種には属さないことが分かっています。
興味深いこの生き物の生態に迫ってみましょう。
目次
ヌタウナギとは、海に生息している細長いヌタウナギ科の生き物のことです。
厳密にはウナギの仲間ではなく、ウナギに似ているというだけですね。
もっといえば、魚類でもないのです。
生きている化石と呼ばれるほど珍しいもので、脊椎動物の進化をたどる上でとても貴重な存在とされています。
いったいどんな生態なのでしょうか。
水中を泳いでいるシーンをとらえた動画を見つけましたのでご覧ください。
ヌタウナギの生息域は、かなり幅広くなっていますよ。
以前の説では、深場にしかいないことになっていましたが、最新の調べでは水深5メートル前後にその姿を見つけることができています。
深いところでは、水深200メートルを超える層でも泳いでいるようですから、深海魚っぽい要素はじゅうぶん持っているといえるでしょう。
釣るのはちょっと難しいのでしょうか。
世界中の温帯エリアなら、その姿を見ることができます。
日本ならどこにいてもおかしくはないでしょう。
ヌタウナギの身体の特徴を挙げてみましょう。
まず顎(アゴ)を持っていません。
その皮膚からは、粘液=ヌタが大量に分泌されていて、全身を覆うようになっていますよ。
危険を察知したら分泌するケースもあるようです。
身体の側面には、複数の鰓孔がありますが、これは目ではないので注意してください。
ヌタウナギの口を見てみましょう。
いくつかの口ひげが伸びていて、口の周りには歯がありません。
ただし、舌の上に歯のような突起物があって、大型の魚に吸い着きながらその内部を食べてしまう習性を持っていますよ。
特徴的な口ですから、アップ画像で見てみましょう。
先端部分が口ではなく、指の触れている辺りが内側に窪むようにして開きます。
噛み付いてくる印象は受けませんね。
ヌタウナギのヒレは、尾ヒレのみ存在しています。
他のヒレは見当たらず、実は小脳も持ち合わせていません。
体内に精巣と卵巣がありますが、機能しているのはどちらか一方のみです。
ということは、オスかメスになることを成長のタイミングで決めているのでしょうか。
それとも生活するシチュエーションに合わせて、足りないほうに切り換えているのでしょうか。
とても興味深い生き物ですよね。
ヌタウナギの料理は、日本国内ではあまり見られないのですが、韓国では盛んに食べられているようです。
肉を炒めるかのように、ヌタウナギの身をぶつ切りにして、野菜や香辛料とともに火を通していくのが一般的な調理法でしょう。
調理していて臭いニオイはしませんから、下処理を手早くおこないながら調理するようにしたいですね。
手早く表皮を剥いてから内臓を取り除けば、後は丁寧に焼き上げれば完了です。
生臭さを想定して辛味の強い味付けをするケースがありますが、さほど臭みは出ませんから、通常の調味料で味を整える程度でじゅうぶんではないでしょうか。
骨は軟らかいので、しっかり火を通すだけでコリコリと噛みながら食べることができます。
ヌタウナギは、腐った肉を食べる腐肉食性だといわれています。
例えば、クジラなど大型魚類の死骸を発見すると、そこにヌタウナギがたくさん食い付いていることが多々あります。
当然生きた状態のものも食べていて、ゴカイのような虫系の生き物やエビ・カニのような甲殻類も捕食対象になっています。
また体側には、粘液を放出する孔が並んでいます。
粘液腺から白色の糸状の粘液を大量に分泌するようになっていますよ。
この液を狙った獲物のエラに詰まらせて、窒息させてしまうこともあるようです。
ヌタウナギは、とても生命力が強いことでも知られています。
例えば、包丁で頭を切り落としても、しばらく身体をよじらせていますよ。
また痛いと感じたら、それに対する反射的な動きも見せます。
調理動画の中で、頭が落とされた瞬間体液を大量に分泌させたのも、この反射的な動きの一環でしょう。
どうやって釣ったらいいかイメージしにくいヌタウナギですが、これまでの生態から考えると、ひとつの答えが見えてきます。
まず、底ベタに居るところへ仕掛けを投入すること。
仕掛けと餌を底から切り離さないように、つまり中層や表層に浮き上がらないようにアプローチすれば、ヌタウナギが釣れる確率は上がるでしょう。
アナゴ釣りの外道として、よく釣れているとも聞きます。
カンタンな投げ釣り仕掛けや、ちょい投げ仕掛けを用意して、防波堤などから投入することをおすすめします。
餌はやはり虫餌、ゴカイやイソメなどが効果的ではないでしょうか。

シマノ(SHIMANO) 磯竿 17 ホリデー磯 3号 450 サビキ釣り
振り出し式の外ガイド遠投ロッドです。
仕舞寸法が94センチと短くなるので、持ち運びがとても便利です。
錘負荷の設定が、8号までとなっていますから、防波堤からでも沖合いのポイントに届けることができますよ。
投げ釣り用の仕掛けを用意して、天秤やオモリを装着し底を丁寧に探るようにしましょう。
アナゴ釣りをする目的で気軽にアプローチするほうが、ヌタウナギに遭遇しやすいかもしれません。

シマノ(SHIMANO) スピニングリール 19 シエナ C3000 3号 150m糸付 エギング シーバス ライトショアソルト
3号のラインが150メートルも巻かれたセット販売専用のスピニングリールです。
とてもコスパが優秀で扱いやすいのが特徴ですね。
自重も250グラムに抑えられているので、ロッドを振り抜いてから支えやすいでしょう。
最大ドラグ力が8キロもあるので、しっかりフッキングできるのが嬉しいですね。

ウナギやアナゴ釣りに使う仕掛けですが、ヌタウナギにも有効です。
各部に蛍光カラーを施してあるので、夜釣りに適していますよ。
餌の位置を感知しやすいので、食い付いてくる確率は上がるでしょう。
飲まれても確実にフッキングできるフックですから、安心して待ちの釣りを楽しめます。

遊動式の天秤にしておくと、ヌタウナギが食い付いてきた際のアタリが、手元で判別しやすいでしょう。
底に根掛かりする確率も低いので、大胆にさまざまなポイントを攻めることができます。
天秤アームの曲げなど、自分なりに仕掛けを工夫して作り上げてみましょう。
遠投を試みるときは、ロッドティップからの垂らしを長めに取ることを心がけてください。
あまりに短いと、ラインがロッドティップに引っ掛かって、最悪の場合はロッドを折ってしまうかもしれません。
垂らしには気を配りながら、何投も投げていく中で飛距離を伸ばすことを意識しましょう。

マルキューからリリースされている、虫餌ワームです。
常温で保存できるので、餌を手配しなくても釣りを始められますよ。
常にタックルボックスの中に入れておき、ヌタウナギが狙えそうな釣り場なら取り出して使ってみましょう。
遠投しても身切れしにくく、ハリ持ちがいいので食い付いてくる確率もアップします。
ゴカイに似ている赤色系のほうが、ヌタウナギが食い付くような気がするのですがいかがでしょう。
ヌタウナギの特徴や習性、食べ方・釣り方、釣りならそのためのおすすめアイテムなどをご紹介しましたが、いかがでしたか?
相当深いところにいますから、防波堤から投げるだけでは釣れない!と考えるかもしれません。
でも意外な水深のエリアで、釣れてしまうこともあるのです。
ヌタウナギの釣り方にセオリーはありません。
思いついたアプローチを積極的に実践して、この珍しい魚を釣り上げてみましょう。
ウナギ釣りを完全解説!天然うなぎの釣れる時期、エリア、仕掛けなど全てに答えます
近所の河川や都会のオフィス街の河川でもウナギが釣れることを知っていますか? さらにウナギ釣りはシンプルな仕掛けで挑戦でき、難しいテクニックも不要なので初心者でも簡単です。 こ…
FISHING JAPAN 編集部ヒイラギって魚知ってる?釣り方からさばき方、おすすめの料理法まで一挙ご紹介!
みなさんは“ヒイラギ”をご存知ですか? 恐らく最も馴染み深いのはクリスマスに飾る植物だと思いますが、実は魚の中にもその名を持つものがいます。 防波堤釣りなどで群れになって泳ぐ…
FISHING JAPAN 編集部オジサンってどんな魚!?ババアって名前の魚もいるの!?変な名前の魚の由来や捌き方をご紹介します!
釣り人の皆さん、オジサンという魚を釣ったことはありますか? オジサンなんて面白い名前がついている魚って、珍しいですよね! 名前のイメージからは裏腹に、見た目は赤い色をしていて…
FISHING JAPAN 編集部古代魚を水槽で飼育してみたい!熱帯魚で人気の高い古代魚を集めてみた
何やら化石が泳いでいるかのような姿をしているのは、古代魚と呼ばれる魚です。 熱帯魚ショップなどで実際に販売されていて、特に大型に成長するものや珍しい形・習性を持つものは、人気が…
FISHING JAPAN 編集部MONTHLYランキング