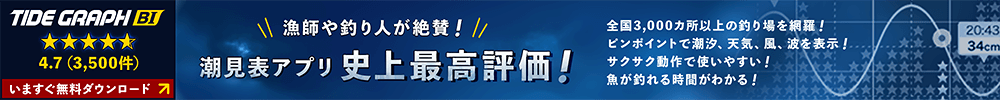MONTHLYランキング

魚には人間にはない感覚器官がある!?嗅覚が人間の300倍鋭い魚も!?魚達の能力がスゴすぎる!
水の中で生活する魚には、人間にはない特異な能力があります。
そのひとつが絶対音感を持った魚が多いことですね。
人間も小さいころからピアノなどを習い、絶えず音に親しんできた人の中には、絶対音感を持った人もいるのですが、人類全体からいえばわずかなものです。
ところが魚の世界では、わずかな音の違いに気づかなかったばかりに外敵に襲われたり、エサにありつけなかったりと生死にかかわる事態だけに、その音感は絶対なのです。
今回はそんな魚の能力にまつわる豆知識を詳しく見ていきましょう!
音で求愛行動する魚!?
よく海の中は、沈黙の世界だと紹介されますが、あれは真っ赤なウソで、実にさまざまな音に満ちているようです。
お互いに音を出し合って仲間の確認や求愛をしたりすることで有名なのが、関西でグチと呼ぶシログチです。
この魚は、求愛行動するとき、大きな音を出すため、ダイバーなどはやかましくて水に潜っていられないといわれるほどです。
たしかに、この魚を釣り上げてイケスなどに生かしておくと、ぐーぐーと音を出しうるさいですよね。
魚の音にまつわる実験も?
魚は外敵が出す音を関知して逃げたり、仲間や他の魚がエサを食べるときの音を素早く察知してその場所へ集まってきます。
このような習性を利用して海洋放牧場の実験が始まっていますね。
ある程度その地域に定着する魚を選び、稚魚を育てるとき、エサをやる時間に毎回同じ音楽を流し餌付けしてしまうと、しきりのない海へ放してもその音楽を流すとエサがもらえると思って集まってくるそうです。
カツオの一本釣りで最初だけイワシのエサを撒き、あとは散水だけで群を引き留めておく漁法も、イワシが群れ騒ぐ音を利用したものなんです。
聴覚や嗅覚が発達した魚達
海の中ではいくら透明度がよくても見えるのはせいぜい40m止まりだといわれています。
そのため魚は視覚に頼るより、聴覚や臭覚が発達したのですね。
人間の聴覚は、40~6000ヘルツぐらいだといわれますが、魚の中には16ヘルツという低周波から13000ヘルツという高い周波数まで聞き分けることができるものもいるそうです。
魚の嗅覚がすごい!
魚が聴覚以上によく発達しているのが臭覚(嗅覚)でしょう。
その能力は人間の300倍近くも鋭いといわれる魚がいます。
このような感覚器官のほかに魚には味蕾(みらい)と呼ばれる味覚をかぎわける器官があり、水中に溶け込んでいるさまざまな成分をかぎわけることができるそうです。
未だ謎とされるサケの母川回帰も、このような器官を使って自分が生まれた川のにおいや水に含まれている成分をかぎわけて戻ってくるのではという説が有力ですね。
魚に人間にはない感覚器官が!?
視覚や触覚以外にも、魚には人間には存在しない特殊な感覚器官があります。それが、全身を縦に通る側線という機能です。
この側線というものは、魚にとってセンサーの役割を果たし、水の圧力や流れ、波動または音を検知する非常に敏感な感覚器官となっています。これによって、水中の岩や海草の存在と距離を把握することが可能となります。
その結果、水族館などでは照明を消して完全に暗くなっても、魚は自由に泳ぎ続け、ガラスの壁に衝突するということはありません。
また、サーディンなどの小型の魚が群れをなして泳ぐ時でも、お互いが絶えず一定の距離を保ちつつ泳ぎ、ぶつかることはなく、急な方向転換でもすぐに追従できるのは、水中の微細な振動をキャッチできる側線というセンサーがあるおかげです。
人間では経験できない魚の能力、それは本当に素晴らしいですね!
「釣りニュース」カテゴリの人気記事
- 趣味の魚釣りが副業になる?!釣った魚を売る方法を紹介!
- 18イグジストの全機種ラインナップが判明!驚愕のスペックと軽量・防水へのこだわりに注目!
- 竿に表示されている「オモリ負荷」って何のこと?素朴な疑問にお答えします!
- ヌートリアって見たことある?水辺に生息する特定外来種・ヌートリアの特徴を紹介!
- 釣り名言5選!!これを読めば今すぐアナタも釣りに行きたくなる!!
- ブラックバスの歴史を紐解こう!なんとはじまりは1925年に遡る!歴史を知れば釣りがもっと楽しめるかも!?
- ギマって知ってる?外道なのに可愛くて超ウマい!捌き方や食べ方、毒の有無も含めてご紹介します!
- ベイトリールのメリット、デメリットって?その特徴や使い方をもう一度おさらいしてみましょう!【保存版】