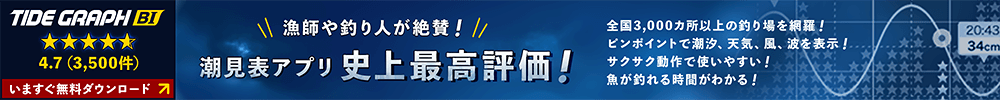MONTHLYランキング

赤身魚と白身魚ってどうして赤いの?白いの?気になるその理由を大公開!
魚には赤身と白身と呼ばれるものがあります。
呼び名通り筋肉が赤く見える魚を総称して赤身魚と呼び、筋肉が白く見える物を白身魚と呼びます。
赤身の代表的な魚といえば、マグロやカツオ、サバやサンマなどですね。
一方、白身と呼ばれる魚はカレイやヒラメ、マダイなどが代表的なものです。
私たちが食べている魚の身は筋肉ですが、どうして筋肉に色の違いが出るのでしょうか?
魚の運動量によって決まる
筋肉に色の違いは魚の運動量によって決まる、というのが正解のようです。
赤身の代表的な魚、マグロやカツオは常に泳ぎ回っていて大移動します。
この豊富な運動量を支えるために、常に海水から酸素を取り入れ運動をつかさどる筋肉に補給し続けなければならないのです。
泳ぎを止めると酸素が供給されなくなって死んでしまうかわいそうな魚なんですね。
白身魚は赤身魚と運動量が違う!
ところが代表的な白身魚、ヒラメやカレイなどは、海底の砂に埋もれ獲物が近付くのを待っていて、獲物が見つかると飛びかかって補食するだけですからあまり運動しなくても生きていけるのです。
つまり、赤身の魚と白身魚は、運動をつかさどる筋肉の使われ方が全然違うのです。
よく筋肉を使う魚ほど大量の酸素を必要とします。
この酸素を筋肉に運ぶ役目をするのが血液ですね。
そして、筋肉の色は血液中にある血液色素タンパク質のヘモグロビンや筋肉色素タンパク質のミオグロビンと呼ばれる赤い色素が多いか少ないかで決まるわけです。
ヘモグロビンやミオグロビンの量がポイントだった!
ヘモグロビンは酸素を運搬する役を担っており、ミオグロビンは酸素を蓄積し必要なときに供給する役目をもっています。
そのため、運動量が多く、酸素をたくさん必要とする赤身魚は、筋肉中のヘモグロビンやミオグロビンが白身魚より多く蓄積されているため身が赤くなるのです。
ちなみに色素タンパク質の量は、赤身は筋肉100g中に150mg含まれるのに対して、白身はわずか10mgしか含まれないそうです。
この違いで赤身か白身が決まります。
日頃食べている魚がどのように赤身・白身になっているのか考えるだけでも面白いかもしれませんね♪
「釣りニュース」カテゴリの人気記事
- ヌートリアって見たことある?水辺に生息する特定外来種・ヌートリアの特徴を紹介!
- 18イグジストの全機種ラインナップが判明!驚愕のスペックと軽量・防水へのこだわりに注目!
- プロアングラーを目指すにはどうすればいいの!?釣りを職業にするには、釣りが上手いだけではダメなんです!
- 趣味の魚釣りが副業になる?!釣った魚を売る方法を紹介!
- 竿に表示されている「オモリ負荷」って何のこと?素朴な疑問にお答えします!
- ギマって知ってる?外道なのに可愛くて超ウマい!捌き方や食べ方、毒の有無も含めてご紹介します!
- ブラックバスの歴史を紐解こう!なんとはじまりは1925年に遡る!歴史を知れば釣りがもっと楽しめるかも!?
- 獰猛なピラニアを食べる魚!?15cmの鋭すぎる牙を持つ怪魚・ヴァンパイアフィッシュって知ってる!?