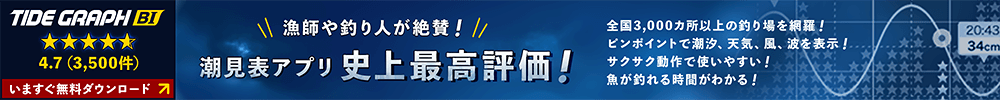MONTHLYランキング

ヒラメの謎に迫る!ヒラメってカレイとどう違う?その見分け方から驚くべき生態の変化、釣法まで、奥深いヒラメの全容をじっくりと解き明かします!
皆さま、ヒラメやカレイと聞くとどのような魚を思い起こしますか?
その体は扁平で、目は魚体の一側に位置し、背面は茶色く、腹面は白色で海底を這う...といった具体的なイメージでしょうか。
ヒラメとカレイは一見すると似た形状をしており、判別に悩まされる魚の一例ですが、それぞれヒラメ科とカレイ科に明確に区分され、食性や生息環境も顕著に異なります。
この度は、カレイよりも遥かに大きな肉食性の魚、ヒラメにスポットを当て、その詳細を深く見ていくことにしましょう!
左ヒラメに右カレイとは限らない!食卓のヒラメはすべてメスの時代がやってくるかも!?
ヒラメはカレイ亜目ヒラメ科の魚で、北海道から九州までほぼ日本全域に棲息してます。
ヒラメの語源「ひら」は、平たいという意味で、「め」は魚の接尾語だと言われています。
地方名も多く、新潟ではオオガレイ、九州ではオオグチガレイ、特に大型をトイタと呼ぶ地方もあります。
関東では出世魚のひとつで、1kg以下をソゲ、2kgぐらいまでを大ソゲ、それ以上大きいものをヒラメと呼んでいます。
昔から釣り好きの間で、左ヒラメに右カレイと言われていますが、これはよく似た2匹の魚を見分けるために表現した言葉です。
尻尾をつかみ、頭を下にして背側を手前に、白い腹側を向こう側にして魚をぶら下げた時、目が左側に寄っているのがヒラメで、右側に寄っていればカレイということになります。
ただし、どこの世界にも天の邪鬼はいるものですね。
カレイという呼び名がついていながら、目が左側にあるヌマガレイがいますし、ヒラメ科の魚でありながらテンジクガレイと呼ばれるヒラメもいます。
カレイとヒラメは、知れば知るほど奥が深いですね。

ところで養殖物と天然物のヒラメの見分け方ってご存じですか?
ヒラメは養殖も盛んなため、市場に出回るものの大半が養殖物だと言われていました。
養殖物は稚魚から丁寧に育てても白い腹側に黒い斑点が出てしまうため、今まで一目でその違いが分かりました。
しかし近年、養殖技術が進んで、今では黒い斑点がでない養殖ヒラメが登場していますね。
この原理は実に簡単で、養殖する水槽の底に砂を敷き詰めて育てるだけで黒斑が出ないことが分かったのです。
さらにバイオテクノロジーの技術が魚の養殖にも導入され、進化しました。
ヒラメはメスの方が成長が早く大きくなるため、飼料を大量に使う養殖では、成長の早いメスばかり養殖した方が効率がいいわけです。
すでに、遺伝子を操作してメスばかりを発生させる技術が実用化の段階にあるそうです。
そのうち私たちが口にするヒラメは、全部メスなんていう時代がやってきそうですね。
ヒラメの目は、生まれた時は両側についている?
ヒラメとカレイの違いは食性にも現われていますね。
カレイは海底に住むゴカイなどの虫類や小型のエビ類などを主食にしていますが、ヒラメは典型的なフィッシュイーターで、主食は小魚、特にイワシ類が大好物です。
このため、ヒラメは歯が鋭く、口も大きいので大口ガレイと呼ぶ地方もあるのです。
ヒラメはカレイに比べて遥かに大きくなり、中には1mを超えるものも棲息しています。
これほど巨大になると昔の引き戸ぐらいの大きさになるため、トイタという呼び名が誕生したそうです。

さて、ヒラメはなぜ目が片方に寄っているのでしょうか?
これは生まれた時から目が片方に寄っているのではなく、環境に適応しながら自然にそうなったのだと言われています。
実はヒラメの目は、生まれた時、普通の魚と同じように体の両側についています。
ですから稚魚は背を上に、腹を下にして普通の魚と同じように泳いでいるのです。
しかし、生後10日目ぐらいから右の目が少しずつ移動を始め、25~30日ぐらいで頭の真上に達し、約40日で完全に左側へ寄って底性生活に入るそうです。
驚いたことに、カレイはこれとは全く逆で、左目が移動して右側の目に近づくのです。
ヒラメの旬は冬!夏ビラメは猫も食わない?
ヒラメといえば冬を代表する高級魚の1つですね。
旬は晩秋から冬にかけてで、寒ビラメと呼ばれ、寒い時期は2~3キロの天然物を最上とするそうです。
ところが同じ魚なのに、4~6月に産卵を終わったヒラメはネコマタギとも呼ばれ、“夏ビラメは猫も食わない”という俗言さえあるのです。
ヒラメは船からの釣りだけでなく、陸っぱりと呼ばれる陸からの釣りも盛んです。
どう猛な魚食魚でルアーにもよく反応するため、外洋面した砂浜や河口などのポイントでスプーンなどの金属製のルアーをキャスティングしながら狙うことが多いですね。
船釣りでは、生きたイワシや小アジのエサを鼻掛けにして泳がせて釣る、ノマセ釣りが盛んです。
この他にも、落とし込みと呼ばれる釣り方で狙う地方もありますね。
縁側が特に美味!

ヒラメといえば薄造りが美味しいですね。
適度な歯ごたえとほんのり甘い身を持つ白身魚ですが、特に美味しいのが縁側と呼ばれる部分です。
これは担鰭骨(たんきこつ)と呼ばれる鰭の部分に付いた肉で、泳ぐ際よく使う筋肉なので、他の部分よりも身が締まって歯ごたえもあり、美味しいと言われています。
昔の謎かけにこんなのがありました。
「ヒラメとかけて、夏の座敷と解く」
その心は?
どちらも縁側がよろしいようで…。(笑)

釣り人の皆さん、今回はヒラメの生態についてご紹介しましたが、いかがでしたか?
ヒラメについて新たな発見や驚きがあったのではないでしょうか?
ぜひ釣り人の皆さんも、船釣りや陸釣りなど、様々な釣り方に挑戦して、ヒラメ釣りを楽しんでください!
「釣りニュース」カテゴリの人気記事
- ヌートリアって見たことある?水辺に生息する特定外来種・ヌートリアの特徴を紹介!
- 趣味の魚釣りが副業になる?!釣った魚を売る方法を紹介!
- 竿に表示されている「オモリ負荷」って何のこと?素朴な疑問にお答えします!
- 18イグジストの全機種ラインナップが判明!驚愕のスペックと軽量・防水へのこだわりに注目!
- ベイトリールのメリット、デメリットって?その特徴や使い方をもう一度おさらいしてみましょう!【保存版】
- キッシンググラミーという熱帯魚をご存知ですか??キスする姿が可愛い魚です!
- ギマって知ってる?外道なのに可愛くて超ウマい!捌き方や食べ方、毒の有無も含めてご紹介します!
- どんだけデカイの!!北海道に出現!「流氷の天使」クリオネが大きすぎてこのサイズなら釣れるかも(笑)