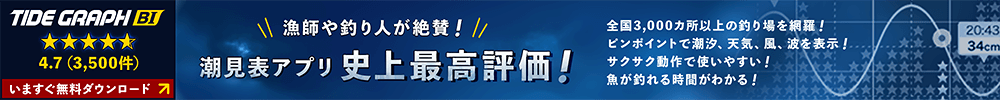MONTHLYランキング

渓流でもバスは釣れる!河川の上流部にまで上っているバスを探してみよう
河川の上流部へ向かうと、どんどん渓流っぽい雰囲気に変わってきます。
まさかこんなところにまで、バスが上ってきているはずはないと考えがちですが、果たして本当にいないのでしょうか?
水質が澄んでいますから、魚の姿を見つけることは容易です。
双眼鏡や偏光グラスを駆使して、バスを探してみることにしましょう。
ダムのある河川の上流部ならバスが上っているかも
本来なら河川の上流部には渓流魚が棲みついていて、釣りをするとイワナやアマゴなどが掛かってきます。
バスの姿は見当たらないはずですが、下流に貯水しているダムがあるところではどうなるでしょう?


雨による増水でバスの棲息域が拡大
大雨が降れば河川は増水し、ダムの貯水量も増えます。
そうなると、本来水に浸かっていなかった場所が、水没してしまう可能性が出てきますよ。
河原だったところが川底に変わったら、ダムに棲んでいたバスが進入できるようになるわけです。
瀬を越えて渓流域へ進入することも
例えば、画像のような川底が見えているチャラ瀬のままでは、体高のあるバスは行き来できません。
ここが増水すると、一気に上流側へ向かうことができるようになり、バスの棲息域が広がることになります。
こういった瀬は、ダムからインレットへ向かえば、あちこちに見つけることができますから、バスはそこを越えてゆくわけです。

上流部に取り残されたバス
バスが瀬を越えた後、水位が元通りに戻ってしまえば、バスは上流部に取り残されることになり、そこを棲み処として定着していくことになります。
冬の水温が極端に下がらない限り、バスは死滅することなく増え続けるでしょう。
そのうちの1匹が渓流域でアマゴに混じって釣れたとしても、何ら不思議ではありません。

河川の上流域、すなわち渓流エリアでバスを探そうと思ったら、画像のような水深のあるエリアをチェックしてみましょう。
岩などのハードストラクチャーや漂流物カバーが存在するエリアなら、バスの姿を確認できるかもしれませんよ。
ミノーやノーシンカーワームのドリフトアプローチで、バスを誘うところから始めてください。
注意しなければならない点は、その河川にアユやアマゴが放流されている場合です。
そこで釣りをするには遊魚料を支払っているはずですから、釣行前に必ず確認をしてください。
管理している地元漁協の指示にしたがって、釣りをおこなうようにしましょう。


「釣りニュース」カテゴリの人気記事
- ヌートリアって見たことある?水辺に生息する特定外来種・ヌートリアの特徴を紹介!
- 趣味の魚釣りが副業になる?!釣った魚を売る方法を紹介!
- 18イグジストの全機種ラインナップが判明!驚愕のスペックと軽量・防水へのこだわりに注目!
- ギマって知ってる?外道なのに可愛くて超ウマい!捌き方や食べ方、毒の有無も含めてご紹介します!
- カサゴとウッカリカサゴは別の種類の魚なの?簡単な見分け方は味や釣り方だった!唐揚げや煮付けなどおいしい料理もご紹介!
- 竿に表示されている「オモリ負荷」って何のこと?素朴な疑問にお答えします!
- どんだけデカイの!!北海道に出現!「流氷の天使」クリオネが大きすぎてこのサイズなら釣れるかも(笑)
- ブラックバスの歴史を紐解こう!なんとはじまりは1925年に遡る!歴史を知れば釣りがもっと楽しめるかも!?