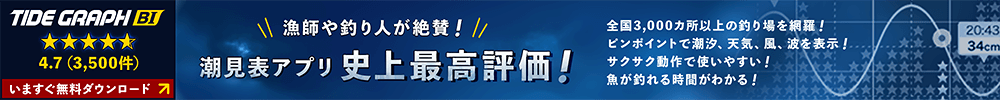DAILYランキング
カワハギ初心者必見! がまかつテスター3人が伝授する1尾への近道 ~ポイントを押さえれば 誰でも難敵・カワハギはゲットできる!~
アタリを出さずにエサをかすめ取っていくこともあることから“エサ取り名人”の異名を持つカワハギ。
ハリ掛かりさせるのが難しく、そのゲーム性の高さから大小問わず、数多くの競技会が開催されるなど、釣り人を熱くさせるターゲットだ。
そんな競技性の高さゆえに難しい釣り・・・という印象も強く、初心者の中にはハードルの高い釣り物というイメージを持っている人も少なくない。
だが、そんな難敵のカワハギを攻略するポイントとして「魚からの情報をしっかりと感じることができれば、本命をゲットするチャンスは大きく増えてきますよ」と語るのは鶴岡克則さん。
三石忍さんも「雑な釣りをしないこと。丁寧な釣りこそ本命を手にする近道です」と語ってくれた。
そして、私・田中義博が重視しているポイントは“常にフレッシュな状態をキープするためにもハリ交換を惜しまない”こと。
今回は、がまかつ船フィールドテスターの3人が、どんなアプローチでカワハギと向き合っているのか・・・をテーマに、カワハギ釣り初心者の方に参考となるヒントを聞き出していった。
目次
釣行の様子は動画でもご覧いただけます!
鶴岡克則編:エサの取られ方とアタリが出るタナのリサーチを一番感度の良いサオで探っていく
3人が実釣したのは12月中旬。
千葉県勝山港の萬栄丸さんの午前船にお邪魔してきた。
北寄りの風が冷たい中、まだ夜も明けていない午前6時に出船。
船長の話では港から南寄りのポイントである富浦沖へと船を進めるという。
ここ勝山港近辺のポイントは、東京湾の中でも浅場でのコッパ(小型)ゲームが特徴的。
エリアにおけるカワハギの魚影が濃いため、カワハギが競ってエサを追い、カワハギのエサに対する反応スピードも他エリアに比べて圧倒的に速い。
必然的に魚からのアタリに対応するには、俊敏さや敏感さが要求されるため、使用するタックルも手感度・目感度ともに伝達の速さと精度が重要となってくる。
ここ勝山港をホームグラウンドにしているのが鶴岡克則さんであり、その釣りの組み立てには、鶴岡さんならではのこだわりが見て取れる。
「私が毎回、カワハギ釣りをスタートする上で重要視しているのが、エサの取られ方とアタリが出るタナが何処なのかをイチ早く探ることです。そのため、持参したサオの中でも一番感度の良いモデルを使用して探っていくことをスタート時のパイロットとしています」
この日、3人が使用したロッドは2022年秋に新発売された『デッキステージ カワハギ』シリーズ。
価格帯的には中級クラスに位置するが、カワハギ釣りに求められる基本性能を追求した仕上がりがその特徴。
感度の伝達スピードに優れたカーボンソリッドを穂先に採用している173AC(アクティブコンタクト)と175AR(オールラウンド)。
そして、目感度でもアタリの振幅が大きく出るしなやかなグラスソリッドを穂先に採用した176SS(センシティブセンサー)の3種がラインアップされている。
鶴岡さんがまず手にしていたのは173AC。
「この173ACは、3本の中では最も胴から穂持ちにかけての張りが強く、サオの調子も9:1に仕上げられています。そのため仕掛けをコントロールする上でもレスポンスが良いことに加え、アタリが出た際の伝達率の速さも秀逸です。カワハギが浮いているのかいないのか、そしてカワハギの気配をキャッチできたらエサを追うスピードが速いのか遅いのかも判断しやすいので、私のパイロットとしての釣りには最適な1本です」
実釣は富浦沖の水深23mでスタート。
船長からのアナウンスによると潮の流れはほとんどないとのこと。
その中、鶴岡さんは底上1mから独特のスナイパー持ちで構え、ゆっくりとサオ先の反動を使って仕掛けを揺らしながら誘い下げていき、カワハギからの反応に集中する。
すると「あっ、触った。底上50cmでサワリがあったので、このまま誘い続けてみますね」と話していると、サオ先が誘いとは異なるイレギュラーな動きに変化したタイミングで、サオを立ててアワセを入れた。
断続的にサオ先が叩かれていたが、途中その引きが止まりカワハギと確信。
姿を見せたのは17cmの本命であった。
「サワリがあったので、同じタナで誘い続けていたらハリが口の中に入って首を振ったのでスムーズにアワセに移ることができました」
朝イチで活性が高い個体だったようで、誘いから前アタリ⇒本アタリまで素直な流れで手にした1尾であった。

がまかつ カワハギ竿 デッキステージ カワハギ 173AC(並継 2ピース)
- 最安値価格
- ¥26,879(amazon)

がまかつ カワハギ竿 デッキステージ カワハギ 175AR(並継 2ピース)
- 最安値価格
- ¥26,879(amazon)

がまかつ カワハギ竿 デッキステージ カワハギ 176SS(並継 2ピース)
- 最安値価格
- ¥27,863(amazon)
お世話になった千葉県勝山港・萬栄丸さん
173ACの感度を活かして手にしたファーストフィッシュ
(左)鶴岡さんは、独特なスナイパー持ちのスタイルでカワハギからの情報を手と目で察知している(右)本アタリをとらえたら、右手を支点にリールを持つ左手を立ててアワセを入れる。右手をスライドさせてリールをつかみ、左手でリーリングする
鶴岡克則編:魚の活性に合わせたハリス長のコントロールも重要なキーポイント
出だしからポツポツと本命を追加していた鶴岡さんであったが、中盤にさしかかるとアタリを弾くシーンが増えてきた。
「エサの追い方が少しゆっくりとなって、スタート時と同じタイミングでアワセても、ハリ掛かりが浅くなってきました」と、この時の状況変化を分析。
ここで、初心者の方にも参考となる一手を打つ。
スタート時から状況をすばやく得るために感度重視のセッティングで『競技カワハギ 速攻』の3.5号・6cmハリスをメインに使用してきたが、ここで同モデルの10cmのロングハリスへとチェンジする。
「まず状況を打開する策として、ハリスの長さを変えてみますが、釣り方や誘いのスピードなどは変えません」
短いハリスとロングハリスでは、同じ誘いをしても海中での動きに変化が生まれることは容易に想像できる。
つまり、海中での付けエサの動きのリズムを変化させることでアタリの出方に違いが出るかを確認していくのがその狙い。
すると、その効果はすぐに結果として現れる。
6cmハリスではクチビル周りに浅く掛かることが多かったが、10cmに変えると口の中の深い箇所に掛かるようになり、キャッチ率も一気に高まっていった。
「ほんのわずかなことですけれど、こういった状況変化に合わせた仕掛けのアジャストが、釣れ方のペースを復活させることにもつながります」
その後、鶴岡さんは、さらにカワハギの活性が下がったシーンでは、10cmハリスのセッティングのまま、誘いの組み立てや釣り方のリズムなどは変えずにサオを最も柔軟な176SSへとチェンジ。
海中での付けエサの動きをさらにスローにすることで、ペースを落とすことなく沖上がりの時間までに16尾の本命をキャッチしていった。
「今日のパターンでは、エサを動かす誘いでないとアタリが出にくい状況でした。付けエサを動かす速さやその幅。また、アタリが出るタナの変化を見極めながら、釣りを組み立てることが求められたと思います。ですが、1日通して私はやや高めのタナからの誘い下げ。カワハギの気配を感じたら同じタナでエサを動かす誘いを繰り返す中で、カワハギの活性に合わせてハリスの長さとサオの調子を変化させていきました。カワハギ釣りは難しい釣り・・・と思われがちですが、カワハギからの情報を判断していけば、必然的に本命をキャッチする数も増えてくると思いますので、初心者の方もまずはチャレンジ。ぜひカワハギ釣りに挑戦してもらえたら嬉しいですね」
ハリスの長さは6cmのノーマルに加えて、10cmのロングハリスも準備すると釣り方の幅が増える
ロングハリスに換えて状況を打開。カワハギの口元を見るとハリは口に中に丸飲みにされていた
カワハギからの情報をしっかりと分析して16尾をキャッチ
三石忍編:難しく考えずに丁寧な釣りを心がければ結果は自然とついてきますよ
次に三石さんの釣りに目を向けてみる。
その三石さんの釣りを横で見ていて、いつも感じるのは、どんなターゲットであっても、誘いや釣り方はもちろん、エサ付けや細かな所作、その全てが丁寧なこと。
当たり前のことを当たり前とせず、ひとつひとつをキッチリと確認していて、再現性がとても高い。
結果として、ムダが省かれることによって本命を手にする近道となっている。
この丁寧な釣り方と所作は、初心者にとっても見習うべきポイントであり、事実、この日のカワハギ釣りでも、しっかりと結果として現れていた。
三石さんが最初に手にしたサオは最も穂先がしなやかな176SS。
オモリ着底後、やや高めのタナからフワふわというリズムでサオ先を動かしながら付けエサをアピールさせ、ゆっくりと誘い下げていく。
宙でサワリがなければオモリで底をトントンと根歩きさせる誘いを繰り返していた。
「釣り方が分からないという初心者の方には、まずはオモリで海底をトントンと確認しながら仕掛けを動かす誘いと、しっかりと食わせの間を混ぜる釣り方をおススメしています。メディアでは、いろいろと誘いのパターンも難しく表現されがちですが、このひとつの誘いを丁寧に繰り返す中で、カワハギがどういうアタリを出すのかを体感していけば、必然的にカワハギを手にする近道になると思いますよ」
三石さんは、オモリで海底をトントンと探って誘いを入れたのち、時折誘いを止めて、仕掛けが張らず緩まずのゼロテンションの状態でステイ。
仕掛けを動かす誘いが“動”であるなら、食わせの間となるステイが“静”の状態。
誘いに寄ったカワハギが、しっかりとステイの状態で反応し、次々とサオ先にアタリを出していた。
「エサのアサリの付け方も、基本は水管、ベロ、ワタへとハリ先を順番に進めますが、その装着に時間がかかるなら、水管は取り外してベロとワタに刺すだけでも問題はありません。大切なのは丁寧に小さく装着すること。釣りを難しく考えずに、ひとつの誘いと丁寧なエサ付け。この2点に注意するだけで、カワハギ釣りのハードルはとても低くなると思います」
初心者の方の手本ともいえるべき釣りの組み立てを1日通して実践し、最終的には18尾のカワハギを手にして満船の中でもぶっちぎりの竿頭。
頭でっかちなベテランや中級者にも、とても参考となるシーンであった。
底トントンの誘いから食わせの間を作る丁寧な釣りで、コンスタントに数を伸ばしていく
誘いと食わせのメリハリがマッチしたのか、この日の三石さんが釣り上げるカワハギは良型が多かった
良型がご覧の通り
田中義博編:カワハギとの接点であるハリは常にフレッシュな状態で!
この日、私が釣りをしていて特に注意を払っていたのは海底状況の把握。
175ARを1日通して使用し、2人と同じようにやや高めのタナで付けエサをアピールさせながら誘い下げていき、着底したらオモリから得られる海底の状態に気を配っていった。
オモリから伝わる柔らかな感触は砂地。
これが根や岩盤にさしかかると硬質で響く音となって手元に伝わってくる。
カワハギはこのような海底の状況が変化する場所に付くことが多く、そのようなポイントに入ったらゼロテンションの状態にして、アタリを見極めていった。
だが、この富浦沖のようにカワハギ釣りのポイントは、砂地の平らな場所ばかりではなく、岩礁帯などの根周りも多い。
加えて、カワハギ以外にもベラやトラギス、キタマクラなどのゲストも多彩で、本命以外のアタリも多かった。
そのような環境下で釣りをする上で、私が初心者の方へアドバイスしたいのが“ハリは常にフレッシュな状態にしておく”こと。
「ゲストが掛かっても同じハリを使い続けている人は結構いると思います。アタリが無くても仕掛けは根に触れていたりもするので、知らず知らずのうちにハリ先が甘くなっていることも多いものです。ハリは常に魚との接点になりますから、ハリに注意を払うだけでもカワハギを手にするための近道になると思います」
船のカワハギ釣りは、替えバリ式の胴突き仕掛けを使用するのが一般的。
つまり、ハリを交換するだけで、常にフレッシュなハリ先の状態でカワハギのアタリと向き合うことができる。
ハリを信頼できる状態に保っておけば、誘いもアタリにも集中できる。
初心者の方はもちろん、これまでの経験でアタリがあるのに掛かりが悪い・・・とか、バラシが多い…という方は、今一度、ハリへの意識を見直してみてはいかがだろう。
海底状況の変化を手感度で察知し、根のキワでアタリをとらえた1尾
10cmのロングハリスにチェンジした直後にキャッチした1尾。ハリは常にフレッシュなものに替えておくことで安心して釣りを組み立てられる
“サオ先は目線の高さ”がテスター3人の共通項
初心者の方々へ1尾を手にするための近道・・・として、3名それぞれの視点からヒントを語ってもらったが、テスター3人の釣り方を見る中で、最も初心者にアドバイスしたい共通項を見つけたので、ここに紹介したい。
鶴岡さんは、左手でリールをパームし、右手はサオ尻を軽く支える独特のスナイパー持ちで釣りをする。
一方、三石さんは釣座に座って右手でリールを軽く包み込み、誘いも右手主導でリードしていた。
そして、私は右手でリールを持ち、左手はサオの胴部分を支え、細かな誘いもこの左手で行っている。
釣りをしているスタイルこそ3者3様であったが、共通していたのはサオ先の位置。
仕掛けにまとわりつくようなカワハギの気配や、ハリを噛むようなわずかなシグナルは、サオやリール越しに手感度として得ながらも、本アタリを見極めるサオ先に出る目感度のアタリは、3名ともしっかりと目線の先にあった。
目線の先にサオ先があれば、僅かな変化も見逃しづらくなる。
アタリを見極める際にサオ先を下げて構えている方や目感度でのアタリが取れない・・・という方は、ご自身の構えを見直してみては?
鶴岡さんのスナイパー持ちスタイル。サオ先はしっかりと目線の先にある
(左)三石さんは終日座って釣りを組み立てていた(右)三石さんのサオ先もしっかりと目線の先で構えている
(左)右手はリール、左手でブランクスを支えて誘う私の構え(右)サオ先をやや立てて構え、やはりサオ先は目線の先でアタリを見極める
初心者の方もポイントを押さえて難敵・カワハギを攻略しよう!
エサをフォーミュラしてチャンスを増やそう!
カワハギ釣りで使用されるエサは剥き身の生アサリ。
塩で締める・・・というのがよく知られているが、専用の添加剤なども数多く発売されており、釣り人それぞれにアサリへのこだわりを持っている。
ここでは、私が普段からおこなっているアサリエサのフォーミュラについて順を追ってお伝えしよう。
剥き身の生アサリには、その表面にぬめりがあり、そのままでは滑りやすくハリに装着しづらい。
そこで、ヌルを取る専用の溶液(マルキユー ヌルとり5)で軽く洗った後、海水で再度洗浄している。
この状態をベースにして、アサリを適度に塩分で締め、なおかつ魚が好むアミノ酸とフェロモン系の特殊誘引剤〈マルキユー バクバクソルト〉でフォーミュラ。
この状態で使う分だけ手元に出し、残りはクーラーで保管している。
あとは、エリアごとの食性に合わせて、さらに旨味成分のフレーバー〈マルキユー ウマミパワー〉を追加したり、粉末タイプのアミノ酸の摂餌促進剤〈マルキユー アミノ酸α〉を状況に応じてフォーミュラして使用している。
このアサリのフォーミュラは、あくまでも私のスタイルであり、人それぞれにこだわりもあるはず。
ノーマルのまま使いたいという方もいるかもしれないが、過去に大会で私だけアタリが出ていたこともあるので、ぜひともトライしてみてはいかがだろう。
カワハギ釣りで使用される生の剥き身アサリ
表面のヌルを取る専用剤、特殊誘引剤、摂餌促進剤、各種フレーバーなど、状況に応じてフォーミュラ
カワハギ釣りに求められる基本性能を追求した「デッキステージ カワハギ」シリーズ
ミドルレンジの価格帯でありながら、カワハギ釣りに求められる扱いやすさを追求して誕生したのが、この「デッキステージ カワハギ」だ。
176SS(センシティブセンサー)は、柔軟なグラスソリッド穂先を採用し、目感度によるアタリが増幅。
繊細なアタリを取りやすくなっていることはもちろん、この穂先のしなやかさを利用し、中オモリや集器を多用するヨコの釣りでも威力を発揮する。
175AR(オールラウンド)は、カーボンソリッドトップを搭載。
文字通り、状況の変化に左右されないタテもヨコの釣りもこなすバランスの取れたオールラウンドモデル。
173AC(アクティブコンタクト)は、3本の中でも最もレスポンスを重視した調子に設定。
カーボンソリッドトップを搭載し、情報伝達力の高さからタテでの釣りをメインに組み立てていきやすい。
深場や急流時、活性の高い魚を手返しよく釣っていくシーンにもマッチする。
3種それぞれに個性を持っており、求める釣りのスタイルはもちろん、状況に合わせてセレクトできるシリーズである。
千葉・勝山港 萬栄丸:090-3210-6258
カワハギ釣りに求められる基本性能を追求した「デッキステージ カワハギ」。3種の個性を味わってみよう
がまかつのカワハギロッドには、上位機種として「シーファング カワハギ」もラインアップ。テクノチタントップソリッド2を搭載し、驚異的な感度でカワハギと対峙できる